
突然ですがあなたが好きなギターやベースを使っていく上で不便に思った事はありますか?
私が特に困ったのは変形ギターなどの"ヘッド落ち"です。
この時点でなにについて私が書こうとしているのかピーンとくる方は高確率でHR/HM好きですね。
そんなこと既に知ってるよ!っとおっしゃらず、もう少しだけお付き合いください。
「B.C Richのギターのボディシェイプが凄く好み。」「ボディの軽さでレスポールとは一味違ったSGの音が好き。」「MSGをコピーするからFlying Vを弾くのは必然!」「ダイムバッグ・ダレルを個人的に崇拝している」などなど変形ギターが欲しい、使っている、という方は並々ならぬ情熱で変形ギターユーザーとなるわけですが
その誰もが最初にぶつかるのがヘッド落ちだと思います。
「歪みを深くかけたギターをフィードバックさせながら恍惚とした表情で髪
をかきあげたい」
「開放弦を鳴らしながら左手で客席を煽りたい」
「テクニカルなギターソロを弾きたい」
といった時(!?)や通常の演奏時にもヘッド落ちが邪魔をしてくるわけです。

対策としてペグは軽いものに、ブリッジ・テールピースは重いものにという
ふうにパーツを交換する方法や
キャビティに重りを入れてバランスを調整するという手段も用いられるそうですがそれでは音がかわってしまったり、手間がかかり、キャビティに関しては電装系の付近に物を入れるので思わぬトラブルにつながりかねません。
そこで、オーソドックスですが一番効果があり、ギター自体の特性を変えない方法があります。
実際に変形ギターを使っていた私がおすすめするのが"ストラップを革製のものに変える"ということです。

摩擦でピッタリととまるので左手に余分な力がかからずヘッド落ちのストレスから解放されます。
ヘッド落ちしないギターでも動いている際のずれなど気にならなくなりとてもおすすめです。
何故ヘッド落ちがそのままにされているのか
ところで、何故メーカーがヘッド落ちに対して本体自体で対策を打っていな
いのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。
何故ヘッドに重心がきているままなのか、それは
変形ギターがよく使われるジャンルにはサスティーンと音抜けが必要な要
素だから、という考え方があるかと思われます。(ギターソロなどでチョーキングとヴィヴラートで一音を伸ばし続けたりする場面が容易に想像できますね)
弦を鳴らすとボディやネックが共振し、よく言われる"ボディ鳴り"
となります。
共振するということは弦の運動エネルギーがボディーの振動に使われて、減退が早まります。減衰が早まるということはサスティーンが短くなります。
ヘッドが重いほどネックの共振が抑えられサスティーンがのびる。
この理屈がもっともらしいと思えるような商品が流通しております。
GROOVE TUBEというメーカーで販売されていたFATFINGERをご存知でしょうか。
ビリー・シーンをはじめ数々のミュージシャンに愛用されていましたが、一時市場から姿を消しその後、Fenderブランドで復活を遂げ、今に至るという代物なのですが、
その商品がヘッドにつける重りのようなもので重心をヘッドにずらし不要な振動を押さえることで弦に振動を滞留させる、まさにヘッド落ちするギターと同じようなギターにする商品なのです。
話が多少脱線しましたがヘッドが重たいことにも理由があり、楽器のデザインや構造と音楽性というものは繋がっていないようで実は繋がっているのかもしれないですね。

PS.ダレルモデルのRazorbackはヘッド落ちしませんでした…
ギター担当:丹


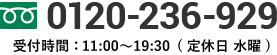



お気軽にコメントしてください。