
熱狂的なファン、使用ミュージシャンも個性的。
サスティナー、GKピックアップ搭載のモデファイなど、他ブランドのエレキギターとは違った盛り上がりがあります。
(玩具の光線銃の音が鳴るスイッチが本体に付けられたりしていますね。)
GLAYのHISASHIさんがギターを弾いていなかったような層にも一躍有名にさせたのもあり、人気のあるモデルです。
ボディ内部は空洞なのでピックガード内にスペースを多く設けられる事情もモディファイしやすく、注目されているギターでもあります。
アルミニウム合金ボディというのが大きな特徴で、存在を知っている方は音が気になって調べたり実際に触りにいったりされたのではないでしょうか。
・ノイズが少ない(外来ノイズに強い)
・雑味のないクリアなサウンド
・鋭い立ち上がりでシャープなサウンド
・特に空間系のエフェクト乗りが良い
などがよく挙げられていますね。
ボディの構造は販売時期によって違いがあることがよく知られています。
1983年当時は2プライ構造で表と裏の2つを中央で溶接してからバリとり、内部が空洞なので発泡ウレタンを注入。
1994年には初期のボディを使っての再販。その完売後に製造されたものは1プライで製造されています。
こちらの1プライも内部は空洞なのでハウリングの問題を避けるために、スポンジ状のウレタンを切り出して内部に挿入しています。
何度も入荷している商品なのですが、同時期に複数本在庫していたことがないので弾き比べなどは出来ていないのですが、この辺りは実際に所有しようとすると気になるポイントではありますね。
ネックはメイプル、ローズウッド指板なので音の個体差はあるのか…ギタリストの興味をそそる存在ですね。
音に関していえば、販売店様のTalboの詳細なページには驚くべきことが語られており
1プライのほうのボディはスポンジ状のウレタンが経年変化して、弾力が失われ内部の残響が変化してギターサウンドに変化があるとの記載がされています。
タルボも経年変化でサウンドが変わる。
まぁ、ネックは木だし変わっていっているのは想像に難くはないですが、意外な要素で驚きました。
そもそも材で音が変わるのか
外来ノイズに強いと言われている点はアルミならではだとして、他の音の特徴は木材同士でも違うし、材がサウンドに影響しているのは固定概念としてあったのですが、別の議論が行われていたのを思い出しました。
材で音変わるの迷信じゃない?という論調です。
ここ数年の間にSNS上で、エレキギターのサウンドに材は関係ない旨を述べた情報発信がなされて注目を集めていました。
・”Tested: Where Does The Tone Come From In An Electric Guitar?”という題でYouTubeに投稿されている動画
・”異なる特性を有するギターの音質再現”という論文
その辺りが話題に登ったのが記憶に新しいところです。
“Tested: Where Does The Tone Come From In An Electric Guitar?”
動画内で音が比較されているのを確認できます。
エレキギターの音で重要なのは電装系。
ピックアップの種類、位置、角度、弦との距離、そしてポットの値を同じにすれば、ボディやネックがない「エアギター」と某ハイエンドギターブランドのギターの音の違いはほとんどわからないという主張のようです。
この動画を見ての個人的な見解はさておき、エレキというだけあって、
「ピックアップの種類、位置、角度、弦との距離、そしてポットの値」が重要な要素であることは確認できる内容です。
位置、角度、弦との距離は「ギターのつくり」やセットアップの状況といえます。
とはいえ、電装系を理想のものにして弦高調整、ネック調整をしても「なにか違う」となった方は大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
最初に動画見た感想が「セイモアダンカン優秀じゃない?」とアホっぽい感想だったのはここだけの秘密です。
論文を読んでみた
論文のほうはネット上で読むことが出来、「高音ではピックアップ交換で音質の変化を確認でき、低音ではピックアップ交換では音質の変化が確認できず。ボディの材質の違いが残響時間に影響を与えていることが考えられる」といった旨が論文内で語られています。
論文まとめの部分に「楽器は,固有の特性により,同一の形状でも音質が異なり,楽器の音質を変えるには材質を交換する事により効果が確認されているが,コストがかかる,希少な材質を使用する場合は入手が困難といった問題があるため,本論文では材質を交換せず,異なる特性を持つ楽器の音質を再現する方法を提案した」となっています。
その一文からも読み取れるように、材によって楽器の音が違うことを認めた上で材以外の要素で音質を近づけよう(変化させよう)とする論文であったことがわかります。
試された方法も「実際の演奏に使用するには今後も検討が必要である。」とまとめられています。
都合の良い部分だけ切り取られて「材で音は変わらない」と主張されてしまったケースだったようです。
むしろ、材によるサウンドの違いを認めた上での実験でした。
やっぱり材での違いはある。
買取で同じ型番が入荷したり、同ブランドの仕様ほぼ同じの材違いが入荷することがあり、ギタリストの性で比較してしまうので断言したいことなのですが、やはりエレキギターの音、材で違います。同型番で個体差あります。
電装系だけでなく、材だけでなく、まだまだ音の違いを生む部分たくさんあります。
「材で音違う」を検証した実験や論文も沢山出回ると良いと思いました。


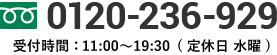



コメント
木材で音が変わるっていうのは宗教と一緒だと思います。
人が聞き取れない範囲での違いはあると思いますが、結局アンプから同じ音が出るので全て気のせいレベルです!!
アンプは信号を増幅させて実際に音を出す部分なので、アンプのサウンドが大きなウェイトを占めているという点においては賛成です。
しかし、自分がギターを買う際は材の仕様違いでつくりがほとんど同じものが店頭に横並びになっていたら両方を試奏してから決めて購入したいと思うのがギタリストなのかなとも思います。
“パーツや仕様の細かな変化や違いも、最終的には全て音に影響してくると考えている。”とロベン・フォード氏がPRSの最新シグネイチャーモデルのページで語っていたり、かすかな差にも敏感になって深みに入っていけるのもギターの面白いところなのではないでしょうか。
「音色」って意味ならほぼ変わらないかなと
でも響き方だったり広がり方、音の伸びは材によって大きく変わるよね
コメントありがとうございます。
いただいたコメントで、「音色」の言葉の解釈や評価の仕方が人によって少しずつ違うのかもしれないと思いました。
・響き方、広がり方、音の伸びを「音色」に含めない考えの方。
・もしくは響き方、広がり方、音の伸びすらボディ材は影響していないと判断している方。
・響き方、広がり方、音の伸びを「音色」に含めたとして果たして本当に「音色」が変わったといえるのかという見解の方。
ボディ材で音は変わらない派の方のなかでもたくさんの確固とした理屈があるのかもしれません。
ボディ材で音は変わる論の肯定派の方は理屈というよりも過去の経験やフィーリング寄りの意見を見ることが多い気もします。
音を作って出している自身の観点ではギター本体を変えて音色が変わったと思っても、それを聴いているメンバーやライブのお客さんが「ギター変えたの?わからなかった。いつもの◯◯さんの音」というのであればボディ材は音色に影響を与えていないとも言えますし…。(観測者を誰とするのか)
どちらが正しいとかを決める内容ではなく「弾いている自分が気持ちよく弾くために”推してる材””推してるピックアップ”などはあったら楽しいですよ。」レベルの話なのかもしれないですね。
物理学が専門のアマチュアギタリストです。
同じ音程(周波数)でも、楽器によって音色が違って聴こえるのは波形の違いに依るものです。波形の違いはメインの波形に乗った高周波成分が原因です。人間の耳は、正弦波単音では20kHz付近までしか聞き取る事ができませんが、波形の違いに寄与する高周波成分としてであれば100kHz付近の音の有無を「音色の違い」として認識できます。
また、エレキギターのピックアップは電源ノイズや空間を漂う電波に影響を受けてノイズを拾う程、高感度です。弦の僅かな振動も拾います。
ボディ材やネック材等の違いに拠る生音の違いはボディやネックの振動から来るものですが、これらの振動を弦が拾う事で、弦の振動に影響を与えます。この弦の振動(弦固有の音にボディ等の振動がフィードバックしたもの)をピックアップが拾い、その信号をアンプが増幅して音が出ます。
なので、当然の事として、(ピックアップの違いやアンプの違い程顕著ではないにしても)ボディやネックの違いは音の違いとして表現されます。
コメントありがとうございます。
>>人間の耳は、正弦波単音では20kHz付近までしか聞き取る事ができませんが、波形の違いに寄与する高周波成分としてであれば100kHz付近の音の有無を「音色の違い」として認識できます。
出ている音の倍音構成や倍音の含まれ方のお話とお見受けします。
音作りで歪ませたり、波形を変えるような加工が積極的におこなわれ倍音構成がコントロールされやすい楽器なだけに忘れがちですが、エレキギターやエレキベース本体は物理現象で説明のつく構造をしている道具ですもんね。
ピックの材質で音色が変わるともいわれることがある世界なので、弦の振動を直に受け止めるボディ材が音に与える影響がないとは言い切れないと改めて思います。
ピックアップ及び電装系以外の要素で音は全く変わりますよ。
因みに現状所有本数はエレキギターだけで27本あります。
その中のメイプルメイン積層材スルーネック&メイプル30%マホ70%ウィングボディロングスケールFRT24Fピックガードマウント重量3.8kgのギターと、メイプルネックコア材ボディロングスケールFRT24Fピックガードマウント重量3.8kgのギターそれぞれ全く同じサーキットで作ったものがあるのですが、両方共リアPUはダンカンカスタム5載せてますけど音は全く違います。
昔トヨタ80スープラとアリストが同じ2JZエンジンを載せて車全体の仕上がりが全く別物だった様に全然違います。
弦高やPU高さ等セッティングも全く同じですが、スルーネックの方はカリンカリンのドンシャリサウンドで頭一つ抜けてサスティーンが長いですが、ハワイアンコアボディの方はレスポール並みの中音主張がありザクザク刻める音で高音の角が丸く、言わば180度真逆な音です。
只歪みデバイスやピッキングへの食い付き感等は同じです、PUが同じですから。
他にもディマジオFREDをリアに載せてるギターが3本ありますけどこれもド素人でもすぐ解るレベルでそれぞれ音が全然違います。
というかストラトだと重量個体差が酷く同一モデル大量在庫品で200g以上差があって普通な訳で、それらお互い出音が結構違うのは弾いた事があれば初心者でも知ってると思うのですけどね。
PUの磁界が拾うのは鉄製弦の振幅であり、弦の振幅運動は張る支点及びそれが取り付けられているボディや指板及びネックと振動を共有するのは中学生でも腑に落とせる物理の話です。
極端に言えば支点部品が取り付けられている先の振動系が似通った振動になるならPUは空中に浮いていても良いのです、PUは飽くまでマイクですから。
それが関係無いかの様な主張が自信満々に出て来るのは発信者の知識不足でしかない訳ですが、売り手スタンスに立てば無知な層の理解を深めた所で高品質品≒利幅の大きな商品が多く売れる訳でも無く、基礎知識や経験のない大衆全体へ向けて難しい話を事細かには説明しないからでしょうかね。
ビジネスなら自動車と同じで言わない方が色々と臭いものに蓋が出来たりそこそこの出来のものをさも凄く良いものの様に謳い売りたいケースもあるでしょうし。
>>歪みデバイスやピッキングへの食い付き感等は同じです、PUが同じですから。
歪み量が多いサウンドメイクの層が”ボディ材は関係ない”と提唱していると仮説を立てたことがあり、”歪みデバイスの反応やピッキングへの食い付き感を最も重要としている層の主張”と言い換えれば仮説は遠からず近からずだったのかもしれないと思いました。
所有本数も然ることながら、仕様を聞いてワクワクするギターをたくさん所有されているようで羨ましいです。
私は”材が全く一緒でピックアップもフロントとリア共に全く一緒、ブリッジユニットも一緒のギター”を同時期に数本所有していたことがあり、違うのはネックジョイント方法か製造ブランドのみでしたが、それでも自分の中で音の印象や使い分けが明確にあったので『××で音は変わる』派の体験談がたくさん集まったほうが個人的には興味深いことをたくさん知れ、自身の中で新たな推論が生まれるから嬉しいと思う昨今です。